江戸の庶民が食べていたもの「どじょう」。漢字で書くと「泥鰌」。江戸時代には「どぜう」と書きました。令和の現在も、浅草などで食べることができる江戸庶民の味です。

値段
どじょうを丸ごと煮込んだ「丸鍋」は下町の名物グルメとして今も大人気です。
江戸時代後期では、柳川鍋の料金は1人前で48文(約960円)くらいだったそうですが、幕末は物価が高騰した時期なのでもっと基本的にはもっとリーズナブルに鍋が食べられたと思います。
栄養価
意外ですが、ドジョウはウナギに劣らない滋養もあります。また鍋に入っているゴボウも精の付く食材とされていたため、江戸時代では暑中に食べるものとされていました。
ちなみに、俳句の世界では「泥鰌(どじょう)」は夏の季語だそうです。
「泥鰌浮いて鯰もいるというて沈む」永田耕衣
どじょうの種類
素朴な疑問が出てきました。
疑問:「どじょう」って、世界中にいるの?どじょうにも種類があるのだろうか。
答え:
(生息域)東アジアに生息していたものが、アメリカ・ヨーロッパにも持ち込まれて生息しているとありました。
(種類)日本産ドジョウ類全33種・亜種を1種類。日本だけでかなりいますね。
その中で、築地東京市場で入手できるドジョウは「カラドジョウ」と「ドジョウ」の2種だそうです。
「カラドジョウ」はほぼ中国産で、大きさが選べて「大ど」と呼ばれる大型も多い。
「ドジョウ」は入荷が不安定で大きさもマチマチ。「大ど」は少ない。
分類すると大きく3つに分けられます。
江戸時代の生息域と生息数
庶民が安価に食べられるだけあって、江戸時代から戦前にかけては東京郊外の水田でいくらでも獲れ、低湿地で水田が多かった東京の北東部地域の郷土料理となっていたそうです。
では、現代では、どじょうを見ることができるのだろうか。
こちらは、令和の今でも各地に生息しているとの調査報告があります。いくつかをあげます。
東京:多摩川、荒川、江戸川水系などの中流から下流域および水田とその用水路などに生息、自然繁殖している。
埼玉:川口市内の調節池のドジョウ調査を実施しました。埼玉県内では、在来種系統のドジョウの生息地が減少傾向にあります。
千葉:県内のほぼ全域に生息していると記されている
東京で「どじょう」を食べる
子供の頃に親に連れられて、浅草の駒形どぜう」に行った記憶が微かにあり。今回、いい機会と行ってきました。こちらは、また別の機会に。
食は文化
なんでも、食べられる時に食べておこう。以前あったお店が無くなってゆく。。あのお店も突然無くなったり。
みなさまも是非。浅草に行った際は江戸の味を思い出に召し上がってみてください。

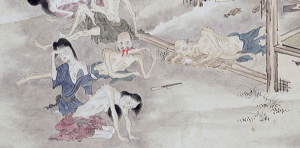






コメント