うなぎは美味しいですよね。夏バテ防止にはうなぎ、とか言いますし。
いつ頃から、どのように食べられてきたのか調べました。
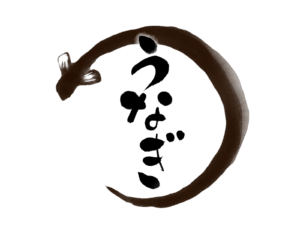
いつから
うなぎは、古くから食べられていて、奈良時代の貴族であり歌人の大伴家持(おおとものやかもち)が知人に勧めたという句が万葉集に残っています。
石麻呂に 吾れもの申す 夏痩せに よしといふものぞ 鰻とり食せ
(石麻呂さん、言わせてください。夏痩せによく効くといわれているものです。鰻を獲って食べなさい。)
昔も高級だったの?
現代のうなぎの食べ方(関東では蒸して食べるよう)になったのは江戸時代です。
江戸中期には、うなぎ飯は一般的な店で1杯64文(約1920円)。庶民はもっぱら屋台で売っている1串16文(約480円)を買っていたといいます。
それから、江戸の幕末の頃になると、200文(約4000円)。現在2500円くらいから、有名店で8000円くらいですので昔から庶民は特別な時にしか食べられないような値段だったのですね。
人口が増え、供給が追いつかなくなったというのも値段の高騰にあるのではないでしょうか。
栄養価
そして、栄養価が高いと言われているうなぎ。うなぎに含まれる栄養素を個別にみていきます。
DHAやEPA:DHAは、脳の発達促進や視力の低下予防・動脈硬化の予防改善、EPAは高血圧予防や炎症を抑える働きが期待できます。
ビタミンA:主成分であるレチノールは、脂溶性ビタミンに分類され目や皮膚の粘膜を健康に保つほか、抵抗力を高める効果が期待できます。
カルシウム:カルシウムは骨や歯の構成成分になる、ストレスを和らげたり血が固まるのをサポートものです。カルシウムを多く含むという牛乳よりも多く含まれています。
ビタミンB1:疲労回復に効果があるB1も豊富に含み、魚介類ではトップクラスに入ります。脚気=当時は江戸煩いと言われる病気(白米の食べ過ぎが原因とされる。)は、玄米でなく(玄米の状態であればB1が含まれる)精米したことによりB1が不足するために起きる。この対策にもなりました。
ビタミンE:抗酸化作用が強いため血中LDLコレステロールの酸化を抑えたり、老化防止、さらには生殖機能を維持する働きも期待できます。
たんぱく質:体を作る構成成分というだけでなく、体の機能を調整する働きもしています。
コラーゲン:コラーゲンは皮膚の弾力を守る働きも期待できる食材です。
上記でご紹介した栄養素が含まれるうなぎは、受験生、高齢者だけでなく家族皆の栄養補給に良いですね。
江戸と大阪・京都の食べ方の違い
- 料理の仕方
まず大阪・京都では、鰻を腹から開き骨を取り除く。こちらの理由は、関西は商人において腹を割って話すという商人文化だったからと言われています。
対する江戸では、腹から開くとは「切腹」のようで縁起が悪いので背開きで調理しました。
また、江戸では、焼く時に一手間をかけて蒸す工程があります。それによりふんわり食感となります。なぜ蒸すようになったのでしょうか。
こちらは、三重県の鰻屋さんのサイトに料理人の立場の答えがありました。
関東は「蒸し焼き」。
うなぎは蒸すことでふっくら柔らかくなります。
ふっくらしたうなぎは大きく見えることから、「見栄を張る」武家文化で好まれるようになったそうです。
また、うなぎを蒸して火を通しておくことで、調理時間が短縮され、せっかちな江戸っ子気質に合っていたそうです。
関西は「直火焼き」です。
蒸さずにうなぎをじっくり焼くことで、うなぎの表面がサクッとなり、中がふんわりな仕上がりになります。その為、うなぎを生から直接炭火で焼くため、時間がかかり、柔らかくするためには職人の技術が必要になります。
ポイントはズバリ、その焼き時間です!
商人はじっくり商談したいため、うなぎの焼く時間が少しかかるくらいがちょうどよかったとか。
https://www.unasei.co.jp/fcblog/unagi-no-kabayaki-kanto-kansai/
なるほどですね。
海外でもうなぎは食べるの
海外でもうなぎはたくさんの国で食べられています。
うなぎ料理の中でも一番多いうなぎ料理は「うなぎの燻製」です。
塩漬けにしたうなぎを燻して燻製焼きします。
その、うなぎの燻製は、ポーランド、オーストラリア、東欧中欧西ヨーロッパなど、様々な国で食べられています。
絶滅危惧種なの?
うなぎは絶滅危惧種です。
絶滅危惧種ですが、生態が十分には分かっていないので、流通を制限するまでは行っていないというのが水産庁の見解のようです。
いろいろな鰻の話
以下のものは、実際に販売されているようです。
うなぎの雰囲気を楽しむ
“ウナギの蒲焼きのタレ”をかけたご飯に、山椒の実を乗せ、卵焼きと漬物を添える。
笑い話の『うなぎ屋の前に行き、匂いだけでご飯が食べる。』の発展系でしょうか。
もどき料理
かまぼこの原料でもあるスケソウダラのすり身に、ウナギの蒲焼きのタレを塗って焼いた「ほぼうなぎ」。カニカマのバリエーションですね。昔からの「がんもどき」とおなじですね。
参考サイトはこちらです。
https://www.ytv.co.jp/ten/corner/gekitsui/zux4a9orlmx9eyye.html#:~:text=ニホンウナギは2013年,倍近く高騰しました%E3%80%82
夏でなくても、うなぎは食べたい。ひつまぶしとか美味しいですよね。
では、また。


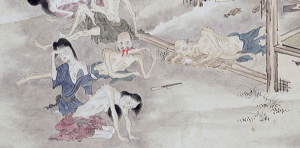






コメント